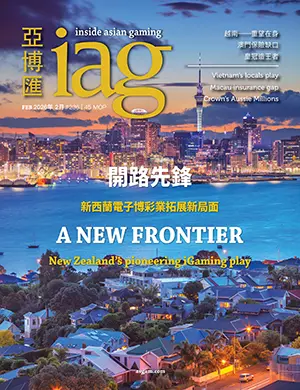この記事の第1部となるIAG 1月号特集記事では、日本での統合型リゾート(IR)開発の論理的根拠、その展開に影響を及ぼす最近の出来事、IR候補地のメリット・デメリット、そして現在の日程などの現状について考察した。第2部では、このレースに参戦する様々な候補事業者を比較・対比していく。
日本は世界の統合型リゾート市場における聖杯、つまりカジノゲーミングのない残り少ない先進経済の一つだ。少なくとも理論上は、日本の統合型リゾートは非常に儲かるはずだ。日本は世界第3位の経済大国でその規模は5兆ドル、一人当たりのGDPは約4万ドルという豊かな国であり、その国民は巨大なパチンコ産業と世界最大の競馬市場から分かるようにギャンブル好きだ。そこに独特の文化、素晴らしい建築・デザイン、そして世界中の人々を惹き付ける洗練された料理を加えてみてほしい。日本のIRが安定した地元市場と、国内外からやってくるコンスタントな旅行客の流れの両方を持っている理由は一目瞭然だ。
過去10年ほどの間に、世界の主要IR企業の全て、(そして他にも多くの企業が)、日本のいわゆる「第1ラウンド」で発行される最大3つのライセンスの1つを獲得しようと現金をつぎ込んできた(注意したいのは、IRライセンス付与の第2ラウンドは、第1ラウンドの7年後にあるかないかという状況だが、第1ラウンドが成功と認識されたかどうかによるという点だ)。候補事業者は、遠くは南アフリカまで、世界中のあちこちから現れていた。(南アフリカとボツワナで12の施設を運営する)ピアモントホテルズは初期の頃に関心を示していたが、現在はレースに参戦していない。

より冷静な者が勝利する
初期の頃は、多くの企業が非常に前向きだった。メルコのローレンス・ホー会長兼CEOの「必要なことは何でもする」という有名な発言がこの感情をまさに言い表していた。しかし最終的に、温かくぼやっとした「日本大好き」という言葉は、非情なビジネス上の決定に道を譲ることになった。世界的な新型コロナの感染拡大もその興奮を冷めさせるのに重大な役割を果たした。日本のIRプロセスが続いてきた中で、大半の規制上の決定が候補事業者に不利なものであったために、多くの企業が途中で挫折し、益々活気がなくなっていった。
2019年始め、私は幸運にも、2万6千語のマカオ大学卒業論文の一環として、13人の非常に経験豊富なアジアIR幹部に長編インタビューを行った。そのタイトルは「とあるアジアの統合型リゾートに他よりも儲けさせるには?」というものだった。この時話を聞いた幹部たちの平均経験年数は27年で、中には何万人もの従業員を抱える数十億米ドル規模の施設のトップもいた。その話をまとめると、アジアのIRの採算性に影響を与える3つの要素は、上から順に
- 近隣地域の大きな人口ベース
- アクセスダイナミクス(訪問客やその金がIRサイトへとたどりつく能力)
- IR賛成派の政府および規制機関(低い税率、有用な労働法、妥当な投資要件等々)
これら3つの重要な要素が現在、日本でライセンス獲得を目指す企業の考えに影響を与えている。例えば、日本のプロセスの最大の問題の1つが、当局が現地の人口ベースが大きく異なるにもかかわらず、大都市と地方のIRを規制上区別していないということ。東京首都圏は世界最大の都市集積地域で、3,800万人の人口を抱える。しかし人口50万人以下の地方の候補地である長崎や和歌山に、全く同じIR要件が設定されている。この誤った等価関係は商業的に道理にかなっていない。

アクセスダイナミクスについても考えてみてほしい。IR誘致に名乗りを上げている大阪や横浜(そして東京、千葉および愛知などの潜在的な候補地)にはすぐそばに国際空港があるが、地方の候補地である長崎や和歌山には重大なアクセス上の問題がある。
コンソーシアム
日本のIRプロセスの初期段階は誰もが自分の身は自分で守らなければならない状態だった。しかし最近では関心を示している企業の幾つかが、コンソーシアムで協力してきている。これは3つの理由から理にかなっている。
1つ目に、コンソーシアムとしてビジネスをすることは日本ではこれまで非常に多く行われてきたことであり、特に大規模プロジェクトの場合はそうだ。カルテル、グループ、コンソーシアムまたは日本語でいう系列、提携など、どのように呼ぼうとも、日本企業にとってグループで営業を行うことは長きにわたって一般的なビジネス慣習となっており、グループ内の各企業が他の企業の一部または全ての株を持ち、そのグループは共通の資金を使い、集団として意思決定さえも行う。
2つ目に、投資額が驚異的な額だということ。大都市の大規模IRでは、100億米ドル(またはそれ以上)という額が平気で話し合われ、「より小規模の」地方型IRでさえも、議題に上がる投資水準は30億米ドル近くになる。ウィン・パレスやギャラクシー・マカオ、そしてシンガポールの2つのIR、その全てにおいて、これまでの合計投資額はおよそ30億米ドルから40億米ドルの間だといえば実感がわくだろうか。これらは、現在ある中で最大かつ最も高級なIRと言っても問題ないだろう。しかし、この2倍から3倍大きな投資水準が日本では話し合われている。コンソーシアムを組成することが、複数の参加企業で巨額の投資を分け合うのに役立つ。

3つ目に、日本版IRを運営するには、様々なスキルや能力が求められる。そしてそれら全てを単独で持つ企業はない。大規模IRを運営するには現地日本の専門知識、そして国際的なノウハウが必要になるだろう。
候補事業者、投資家そしてその他の利害関係者が継続してパートナーを組んでいく中で、レース参加者は減り続けていく。そして一部の事業者は、日本を「難しすぎる」に分類しており、特に気付けばパンデミックに支配されているこの状況においてはその傾向が強くなっている。
日本の事業者
セガサミーは、ゲーム機やキャラクターのソニック・ザ・ヘッジホ ッグで有名な株式会社セガが、パチンコおよびパチスロ機メーカ ーのサミー株式会社と2004年に合併して生まれた企業。以来、リゾート事業も開始。韓国の統合型リゾート(IR)のパラダイス シティを45%所有し、同国カジノ事業者パラダイスが残りの55%を所有している。14億米ドルのIR、パラダイス シティは、ソウルの国際空港に近い仁川に2017年にオープン。セガサミーは、2020年2月に横浜のIRに向け、コンセプトや竣工予想図を公開するとともに、イギリスの建築デザイン会社フォスター・アンド・パートナーズとのいくつもの提携も発表し、横浜のIR誘致を進めていることを明らかにした。セガサミーの里見治会長は、2020年のアジアンゲーミングパワー50で44位にランクイン。息子である里見治紀氏は、代表取締役社長兼グループCOOである。
オカダという名は、IAG読者ならご存知だろうが、岡田和生氏と、同氏がフィリピンで設立したIRのオカダ・マニラを指す。岡田氏は、スロットマシン製造業者のアルゼ、オカダ・マニラの親会社の株式会社ユニバーサルエンターテインメント、そして筆頭株主と副会長を務めたウィン・リゾーツなどを通して、この業界で数十年にわたり活躍してきた。過去10年間のほとんどを苦しい訴訟に巻き込まれた同氏が日本に進出するという確かな話を聞いたことはないが、IRの経験で言えば、他の日本のビジネスマンよりも多いと言える。

ラスベガスの事業者
日本とアメリカには複雑な関係があり、これは第二次世界大戦後の時代にまで遡る。確かにアメリカは、日本に大きな影響力を持 っていたし、現在でも在日米軍基地が23カ所あり、約5万人の人員を抱えている。扶養家族や契約社員を数えれば、この数字は10万人のアメリカ人に膨れ上がる。野球は日本の国民的スポーツであり、一部の日本人は冗談半分で「51番目の州」と自国を呼ぶことがある。
専門家の中には、日本は中国との関係が時に対立していることから、マカオの大手事業者よりもラスベガスの大手事業者を好むのではないかと指摘する声もある。唯一の問題は、シーザーズ、ラスベガス・サンズそしてウィン・リゾーツというラスベガスの主要IR事業者4社のうち、3社が日本でのIR入札から撤退していることである。
ラスベガス・サンズが日本からの撤退を発表後初の収支報告で、当時の社長兼最高執行責任者(現会長兼CEO)のロブ・ゴールドスタイン氏は、「もちろん、努力はしたが、うまくいかなかった。構造が投資家をより歓迎するものであればよかったが、そうではなかった」と述べた。 ゴールドスタイン氏の上司である当時の会長兼CEOシェルドン・アデルソン氏は、「否定的な規制が多すぎて、我々には耐えられなかった」と付け加えた。
これは日本にとって、危険信号である。必要とされる支配的な規制や投資水準に応じたROIに関する深刻な商業的問題があるからだ。また、世界的なウイルス感染拡大が業界を衰退させているという時期的な問題もある。中には、プロセスに結果的に生じた9カ月間の遅れを延長し、全員がより良い長期的な結果を得られるようにすべきだという声もある。

ラスベガスの大手事業者で唯一残ったMGMリゾーツは、大阪の公募(RFP)プロセスで唯一の資格ある入札業者となっている。このように競争相手が欠如したことで、MGMリゾーツと日本のコンソ ーシアムパートナーであるオリックスの原動力は、確実に変化するだろう。MGMリゾーツの前会長兼CEOジム・ムーレン氏は、日本に対して非常に楽観視していたが、彼の後継者であるビル・ホーンバックル氏は、より慎重のようだ。去年7月のMGMの収支報告で、新会長のホーンバックル氏は「IR開発が恐らく遅れること、そしてこの投資に興味を持っている誰しも、特に我々にとってうまくいけばこれをより良い投資にしてくれるであろう話し合いが再開できるということも喜ばしい点だ」と述べた。
マカオの事業者
マカオの6社のコンセッション保有者のうち、MGM、サンズ、ウィンの3社にはアメリカとの繋がりがある。他の3社、ギャラクシー、メルコ、SJMはいずれも、別々の時期に日本への関心を示している。
ギャラクシーは、3社の中で間違いなく最高の立場にいるが、その最も明白な理由は、貸借対照表にある60億米ドルを超える膨大な現金だ。他の5社のマカオのコンセッション保有者が世界的なウイルス感染拡大中に、手元資金を補強するべく借金を進んで増やしていったのに対し、ギャラクシーにはどんな難局でも乗り切るだけの資金力がある。保守的な日本政府は、このような資金力の豊富さに魅力を感じるに違いない。ギャラクシーは、日本国内にある外資系企業の中で最大のチームを擁しており、東京にあるギャラクシー・エンターテインメントジャパンのオフィスでは約25名の社員が勤務している。ギャラクシーは、ギャラクシー・マカオのオークラブランドのホテルで日本の実力をアピールしたり、モナコで158年の歴史を持つSBM(世界的に有名なモンテカルロカジノのオーナー事業者)の株式を5%保有していることで、中国のルーツを弱め、ヨーロッパの趣を強めて入札に臨んだりしている。

マイナス面として、ギャラクシーは日本でかなり長い間活動してきたが、コンソーシアムのパートナーをまだ発表しておらず、日本の特定の場所に焦点を当てていないことが挙げられる。また、現在の4カ所のどれかにギャラクシーが興味を持つかも疑問だ。長崎と和歌山は規模が小さすぎるし、大阪はすでに撤退してMGMに任せているし、横浜はこの記事のパート1でも紹介した通り、問題がいくつもある。その中でも特に重要なのは、来るべき市長選挙と、多くのの横浜市民や一部の市長候補者によるIRへの反対姿勢である。ギャラクシーがライセンスの取得を目指す場合、人口の多い東京(お台場か旧築地市場)か愛知(名古屋にある中部セントレア空港の隣)のいずれかを選ぶはずだが、どちらも公式に宣言しておらず、また、時間切れが確実に迫っている。
そして最終的には、日本がこのような強大な中国企業を受け入れるかどうかという疑問が残る。ギャラクシーは、香港とマカオにルーツを持つ会社であると主張するだろうが、日本ではそう認識されることはないはずだ。
メルコは、15年前から日本に対し、執着に近いものを持ち続けてきた。会長兼CEOのローレンス・ホー氏は、日本への情熱を定期的に見せている。同氏は、「必要なことは何でもする」という有名な言葉に加え、同社が日本のIRライセンスを勝ち取った暁には、自身と幹部チーム全員が日本に移住することを約束した。マカオのシテ ィー オブ ドリームスの旗艦ホテル、モーフィアスには、和式トイレまであるのだ。過去に「大阪ファースト」を貫いていた同社は、現在は「横浜ファースト」に切り替えている。昨年12月、メルコはIAGに対して、ウイルス感染拡大中であるにもかかわらず、日本のIRに100億米ドルを投資する意思があることを認め、パートナーシップの成功を収めた過去の実績を指摘し、「経営と運営には日本の文化が組み込まれている」と主張した。 マイナス面では、公平であろうとなかろうと、メルコの「内容より形式優先のアプローチ」を批判する声もあり、同社が同業他社よりも大胆でリスクを冒していることは間違いない。これが、日本人のデザイン、美、技術への執着を考えたら良いこととして認識されるのか、同国の保守主義を考えたら悪いことになるのかは、まだ定かではない。そして、ギャラクシーに加えてメルコも、中国企業と認識されるであろうと考えている。

SJMは、北海道に関心を見せていたが、北海道が事実上撤退したため、少なくとも第1段階についてはSJMから何も聞いていない。水面下で陳情しているとすれば、とにかく徹底的に黙っていることになる。
サンシティは当然、厳密にはマカオの事業者ではないが、その基盤はマカオにある。これまで、マカオの6社全てのコンセッション保有者にクラブがあるVIPゲーミングのプロモーターを務め、アジア各地に多くの施設を所有してきたことから、大陸全体で幅広いIRサービスを提供し、貴重な経験を積んできた。サンシティグループは、2007年に正式に設立されたが、アジアのゲーミング業界におけるそのルーツは数十年前に遡る。ベトナムのホイアナに施設がオープンしたばかりで、マニラのウェストサイドシティ・リゾートワールドは現在建設中であり、ウラジオストクのティグレ デ クリスタルの過半数を保有し、韓国とカンボジアで事業を展開しているなど、アジア全域でIR事業者への転換を目指す同社の願望は明らかである。

サンシティが世界的に有名な建築事務所AEDASと共同で開発した「IR 2.0」のコンセプトは、「和歌山県の歴史的伝統、自然の景観、文化的エッセンス」を融合させたものだと言われている。同社は先月、和歌山のマリーナを活用し、マリーナシティをヨットの港に変え、スポーツと地域資源を中心とした和歌山のイメージを発信する持続可能な観光を創出することを明らかにした。さらに、F&Bやエンターテイメントの提供など、同社が多様な非ゲーミング分野に長い歴史を持っていることが、今回の入札を後押ししている。同社は素晴らしいことに、現地での繋がり、和歌山のオフィス、日本やアジアのメディアを活用した十分に調整されたPRキャンペーンなどを介して、「IR 2.0」のコンセプトを日本とより広いアジアの業界に向けて惜しみなく宣伝および説明している。
ギャラクシー、メルコ、SJMと同様に、サンシティは中国企業という認識を克服する必要があるが、大手の老舗IR事業者であれば難しいとされる、日本主導のマルチパーティーのコンソーシアムの中に深く食い込んでいく能力を持っている。これは彼らにとって、切り札になるかもしれないのだ。
北米の事業者
ハードロックは、アジアのゲーミングブランドとしても、ラスベガスのアイコンとしても日本では知られていないため、過小評価されがちだ。よく知られているのはハードロックカフェの方であり、1983年に東京の六本木に第一号店をオープンして以来、全国に6店舗以下を展開している。しかし、ハードロックは、アメリカの部族ゲーミングの象徴であり、業界のリーダーであると言っても過言ではない。しかも現在は、拡張モードに入っている。マイアミ近郊にある旗艦施設のギターホテルを含め、世界中に約12軒のカジノを展開している同社は、重要な人材を二名採用して、日本での信頼性を大幅に強化した。一人目は、ハードロック・インターナショナルのアジアCEOであるエド・トレーシー氏。彼は、数十年前から業界で活躍しており、特にマカオではサンズ・チャイナのCEOとして成功を収めた。同氏が早めに打った手の一つが、ハードロック・ジャパンの社長に町田亜土氏を起用したことだ。町田氏は、ゴールドマン・サックスやボストン・コンサルティング・グループなどのビジネス分野で実績があり、政治分野では、米国大統領選挙運動での上級政策担当やアドバイザーなどの役職を歴任。京都大学とニューヨ ーク大学を卒業しており、日本語と英語が堪能だ。ハードロックは先月、その精神的な故郷であるロンドンのザ リッツ クラブのカジノライセンスの取得を発表。なお、1971年には、ハードロックカフェの1軒目が現地に設立された。
これまで、北海道に焦点を当ててきたハードロックは、苫小牧市にある日本最北端の立地を公式に支持し続けているが、長崎やその他の地方都市で候補者として浮上しても驚きはない。トレーシー氏と町田氏は、油断ならない手強いチームであり、何十年にもわたってトレーシー氏と共に仕事をしてきたハードロック会長ジム・アレン氏の信頼と支持を得ている。
2018年、ラッシュ・ストリート・ゲーミングの創業者で会長のニ ール・ブルーム氏は、北海道のIRに20億ドルを投資することを約束した。当時、シカゴを本拠地とする不動産およびゲーミング大手の同社は、北海道に専念すると言っていたが、これは鈴木知事が「環境問題」を理由に、北海道をレースから事実上外す前のことだった。 ラッシュストリートはその後も沈黙を守っているが、IAGは同社が日本に関心を持ち続けていると知っている。地域型ゲーミングを好むことで知られ、利用可能な資本が多いことを考えると、同社は地方の立地を追求しながらも、数十億ドルの投資が必要となることを理解していると考えられる。
日本法人のクレアベストニームベンチャーズを傘下に持つクレアベスト・グループは、カナダ、アメリカ、チリでカジノやリゾートの権益を持つカナダの投資会社。鈴木知事が北海道をレースから事実上撤退させる前(さらにはその後も)に北海道の件で騒がれていたもう一社クレアベストは、和歌山に焦点を移したが、その一騎打ちのレースのライバルであるサンシティとは異なり、彼らからの情報はほとんど得られていない。クレアベストは、彼らが単なる投資家であることを明らかにしたが、どの事業者とパートナーを組むかについては、まだ何も聞かされていない。すぐに大胆に動かない限り、クレアベストがライセンスを確保するのは難しくなる。
他の候補事業者
まだ言及されていない最も定評のある事業者が、ゲンティン・シンガポール。このシンガポールのIR事業者は、大阪、次いで横浜に焦点を当てており、大都市圏への進出を希望していることが伺える。社長兼最高執行責任者のタン・ヒー・テック氏(2020年アジアンゲーミングパワー50で24位にランクイン)は、日本におけるゲンティンの代表として、礼儀正しく、プロ意識が高く、好感の持てる素晴らしい仕事をしており、日本でも高く評価されている。これは、タン氏の上司であるゲンティン・バーハッド会長兼CEOのリム・コ ック・タイ氏(2020年アジアンゲーミングパワー50で5位にランクイン)による、シンガポール支店をゲンティン入札の顔にするための抜け目のない動きだったのだ。日本の権力者が、同国のIR業界を「 世界で最も規制の厳しい業界」にするという目標を何度も繰り返し立てていることから、日本は昔から、綺麗なシンガポールに憧れを抱いてきた。 日本ではすでに定着した、現地人の入場料6,000円にまで、シンガポールの規制の特徴は及んでいる。
ゲンティン・シンガポールは日本でのその手の内を隠しているが、これはマレーシアの親会社が今世紀最初の10年間にシンガポ ールで採用した戦術が成功したもので、その際、非常に切望されていた2つのIRライセンスのうちの1つを確保したのだ。マイナス面として、ゲンティンのビジネスは世界的なウイルス感染拡大の影響で、おそらく世界のどの大手ゲーミング会社よりもカジノクルーズビジネスに大きく関わっていることを考えると、壊滅的な打撃を受けている点が挙げられる。ゲンティンが世界中で手を広げようとしている時に、これほど悪いタイミングはない。43億米ドルのゲンテ ィン・ラスベガスが完成間近の中、リゾーツ ワールド ニューヨークとマレーシアで自国運営を行うリゾーツ ワールド ゲンティンはともに、ウイルス感染拡大の憂き目に遭っている。リム・コック・タイ氏の息子であるリム・ケオン・ホイ氏(2020年アジアンゲーミングパワー50で30位にランクイン)は、クルーズ事業でウイルス感染拡大関連のトラブルが発生する中、流動性を維持するために債権者への支払いを全て停止した後、8月にゲンティン香港の副CEOを退任した。
11月には、2020年第3四半期のアップデートの一環として、ゲンティンの日本に関する「開発を継続して監視し、RFPを予想する」というこれまでの文言から、次のより慎重なトーンに変更された。「正式な入札手続きが始まった時にIR事業者公募(RFP)の条件および投資環境を評価し、これらの条件が当グループの投資条件を満たした場合に提案に回答する予定だ」。
これは ゲンティンの最初の欠点になり得るか?
ブルームベリー・リゾーツは、フィリピンで最も成功したIRと言われるソレアのオーナー兼運営会社。同社は日本に関心を示しており、一時は和歌山とのつながりもあった。しかし、最近は動きが非常に静かで、これはおそらく母国のウイルス感染拡大を乗り切ることに集中しているためだろう。12カ月前にIAGから日本について質問を受けた際、会長兼CEOのエンリケ・ラソン・ジュニア氏は、立地、規制、IR費用の見積もりの増加などが明確になっていないことを強調。これは間違いなく、今でもあまり変わっていない。

ナガコープの会長兼CEOチェン・リップ・キョン氏(2020年アジアンゲーミングパワー50で12位にランクイン)は、過去25年間、拡張モードに入ったままだ。同社はメコン川に係留された船として1995年に開業して以来、チェン氏はプノンペンでの70年に及ぶカジノ独占ライセンス、非常に有利な税制と規制体制、そして2006年には香港証券取引所に上場するなど、勝ち続けてきた。同氏は4億米ドルのナガ2を海岸に建設し、35億米ドルのナガ3の開発を 「全速力」で進めている。それだけでは不十分と言わんばかりに、世界で最もウイルス感染拡大の影響を受けていないゲーミング会社としての身分を享受し、ロシアのウラジオストク郊外のプリモリエ・エンタテイメントゾーンで施設を建設中だ。最近では2020年半ばにも日本、特に長崎に関心を示している。その後の進展は特に聞いていないが、いずれナガコープから話があっても驚きではない。
長崎の誘致の件でもう一つの有力候補が、カジノオーストリアだ。CEOのクリストフ・ツールッカー=ブルダ氏は10月下旬、長崎IRの事業コンセプトに応募したと発表し、RFPの入札者として確定した。カジノオーストリアは、1994年から2014年までオーストラリアのカジノ・キャンベラを所有および運営しており、南半球での事業経歴を持つ。

国際色豊かなコンソーシアム
入札企業の中には、すでにコンソーシアムを結成したところもあり、それゆえに資金や可能性を結集して入札を強化している。以下の3つのコンソーシアムは、いずれも長崎IRのライセンス取得を目指す。
カレント、ゲット・ナイス、広東グループ、サクセス・ユニバース、そしてITCプロパティー・グループはコンソーシアムを形成し、さらに多くの企業を含んでいる可能性がある。カレントは、日本の不動産投資を主とするSRCグループの一部。香港に上場しているゲット・ナイスは、マカオのコタイ初となるゲーミング施設、ワルドカジノとグランド・ワルドカジノを運営していた会社だ。グランドワルドは最終的に、ギャラクシーに売却されたのちブロードウェイに改築され、ギャラクシー・マカオ・ブロードウェイの一部となった。広東グループは、マカオを拠点としたVIPゲーミングのプロモーターで、香港に不動産を所有している。ITCプロパティー・グループは、マカオのワンオアシスの住宅開発など、不動産投資を行っている香港上場企業。サクセス・ユニバースは、マカオの内港地域でポンテ16やソフィテルホテルのカジノを運営している。
オシドリとモヒガン・ゲーミング&エンターテインメント(MGE)は、1月の最終週に提携を発表。MGEは、アメリカ国内最大規模の部族カジノの一つ、コネチカット州のモヒガンサンが最も有名である。韓国の仁川に開業を予定している、第一フェーズを現在開発中の10億米ドルのリゾート、インスパイア・コリアは、これまで何度か延期されているが、CEOのマリオ・コントメルコス氏は韓国での展開を繰り返し断言しており、同施設への投資総額は複数の段階を経て50億米ドルになると言われている。モヒガンは昨年、インスパイア・アテネと名付けられた、旧アテネ国際空港のカジノの入札も勝ち取っている。
オシドリはこれまで、アジアのIR業界では無名だったが、2020年6月に子会社であるオシドリ・インターナショナル・ディベロップメントの会長兼CEOにアレハンドロ・イエメンジアン氏を採用したことで注目を集め、長崎IRの入札を同氏に託している。イエメンジアン氏は、ラスベガスの王族に近いと言われる、伝説のカジノ億万長者カーク・カーコリアン氏の長年の右腕との呼び声も高い。カーコリアン氏は、MGMスタジオとMGMリゾーツの大株主であり、数十年にわたるラスベガスのゲーミング業界の大物だ。

イエメンジアン氏は金融界にいた経歴を持ち、ラスベガスのトロピカーナの元共同所有者で、長期間MGMリゾーツの幹部を務めた。そして1999年から2005年まではメトロ・ゴールドウィン・メイヤ ー・スタジオの会長兼CEOを務め、1997年から2005年からは取締役も務めた。MGMの大株主であるカーコリアン氏のトラシンダ社の幹部として、1990年代のほとんども務めている。共にアルメニア系のイエメンジアン氏とカーコリアン氏はとても仲が良く、テニスを一緒に楽しむことも多かった。オシドリは、香港の富裕層が後援についていることで知られている。
2020年8月には、ピクセルカンパニーズ、パルトゥーシュ・グル ープやその他無名のコンソーシアムパートナーが、長崎IRを入札するべく提携を結成し、発表。ピクセルカンパニーズは東京証券取引所に上場し、ゲーミング、eスポーツ、金融技術システム開発、太陽光施設およびリゾート開発など幅広い事業を展開している。吉田弘明CEOはIAGの11月の単独インタビューで、「一人の力ではなく、私たちが持っていないもの、補完できるパートナーを今後も必要としている。参入を公表したことによって、さらなる拡充をはかり、リレーションを加速させていきたい」と述べている。パルトゥーシュ・グループは過去にオシドリと提携していたが、イエメンジアン氏のCEO就任前の2020年5月に提携を解消。不思議なことに、同社がその事実を公表したのは、約3カ月後の2020年8月のことだった。同社はホテル、レストラン、スパ、ゴルフコースに加えて、42のクラブ式カジノ(主にフランスだがベルギー、スイス、チュニジアにもあり)を運営している。その従業員数は、4千名弱である。
次はどこへ?
現在のタイムライン(この記事のパート1で説明)では、未発表の候補地(最も話題になっているのは東京と愛知)は、早急に動かないとIRレースへの参戦が難しいだろう。それが実現しないと、大阪と横浜の大都市2カ所と和歌山と長崎の地方2カ所が残ることになる。

大阪にはMGMの一社だけが残っており、同社は長年にわたって最も熱意ある候補者たちに囲まれていた。しかし、会長の交代、ウイルスの感染拡大、そして唯一の入札者であることから、そのプロセスが妨げられる可能性が高い。横浜は、次回の市長選挙の影響で身動きが取れず、反IR候補が勝ったらどうなるのかが明確にな っていない。和歌山は、候補者がサンシティとクレアベストの二社しかおらず、後者は沈黙が目立っている。これでは、長崎のみで面白いIRレースが展開される可能性があるが、世界最大手のIR企業は、人口の少なさやハウステンボス敷地内へのアクセス難から、この候補地を敬遠している。
また、少なくとも成功した日本企業が一社あれば合点が行き、その明らかな候補はセガサミーだ。同社は、横浜が希望の候補地であると明言している。

そう考えると、おそらく現在の予想とは少し違ったプロセスが展開されるかもしれない。一つの可能性として、IRの拠点候補地と候補者の両方で競争力を高めるために、さらなる遅延が考えられる。もう一つは、東京や大阪のような大都市で本戦を繰り広げる前の試験的位置付けとして、長崎、いやむしろ和歌山で、3カ所どころか1カ所のIRから始める可能性だ。
あとは時が経てばわかるはずだ。