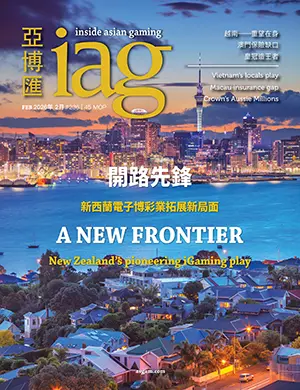IRに関する住民投票の可能性、そして今後の市長選という2つの脅威によって、事業者は横浜市がIR開発計画を最後までやり通すという保証なしで、来年行われる同市の事業者公募(RFO)に参加することを余儀なくされる可能性が高まっている。
そのようなシナリオが現実になり得る可能性の増大は、最近、地元住民の反対派がIR開発に関する住民投票を求めるのに必要な署名数の3倍を集めたことが明かされた結果であり、2021年秋に予定されている市長選を前に林文子市長にはさらなるプレッシャーとなっている。
横浜市は以前、2021年1月から始まる日本政府のIR申請期間の開始までに十分な時間的余裕を残した状態で、2020年中頃にRFPを実施する予定をしていた。しかしながら、その両方がその後、新型コロナウイルスの感染拡大によって延期され、日本政府はIR申請期間を2021年10月まで9カ月間先延ばしにした。
日本を拠点にする業界トップのコンサルタント会社、ベイシティ-ベンチャーズ代表の國領城児氏によると、住民投票となった場合、林市長と市長のIRという夢にとって多くの頭痛の種を作り出す可能性がある。
最短でも住民投票実施は2月になる可能性が最も高いと見ている國領氏は、Inside Asian Gamingに対してこのように述べた。「残念ながら、現実的に見て、IR事業者のコンソーシアムが横浜入札への決定を行うにあたっての変数として、投票結果を考慮するのに間に合う時期に結果が出ることはないだろう。
IR開発計画提出のための国の新日程は、地方自治体がどんなに遅くとも3月にはRFPを開始する必要があることを意味している。しかし、おそらくそれよりも早い。
横浜に関心があるIR事業者とそのコンソーシアムパートナーにとっては、市の政府が住民投票の反対という結果に従って行動するリスクがある中でRFP準備を進めなければならない状況で、その上、来年秋の市長選という重大な政治的リスクもある。皮肉にも市長選は日本政府への提出期間の直前に行われる。
そのようなシナリオを考えると、横浜IRの未来を決める重要ファクターは、ほぼ確実に市長選となり、実施されることが確実ではないことを考えると住民投票は比較的その程度は低くなる。
起こりうる可能性は高いものの、住民投票への最終決定は、既にIR開発と関連予算を承認している横浜市議会に完全に委ねられている。その20万という署名が人口に占める割合はそれでもたった6.6%だということを頭に置いておいてほしい。
同様に、もし市議会が住民投票に同意し、住民がIRに反対票を投じたとしても、その投票に法的拘束力はない。
國領氏はこのように話す。「市民の反対が多数を占めた場合、林市長は『結果を尊重』し、『個人的には』IRレースから快く撤退するというサインを示している一方で、市長が必ずしも市議会をコントロールするということにはならない。IRレースから撤退するには市長と市議会が全力で取り組まなければならないだろう」。
最終的には、結局は全てが事業者次第となるかもしれず、横浜が実質的に今にも誘致を断念するかもしれないと知りながら、RFPに資源をせっせと使いたいかどうかだと國領氏は指摘する。
同氏は、「市議会の決定に関わらず、住民投票という状況は横浜のIRへの取り組み、または参加に関心があるIR事業者にとって事を難しくする一方だ。これらIRに関する政治的問題は、投資家と事業者にとって重大な留意事項である」と説明する。