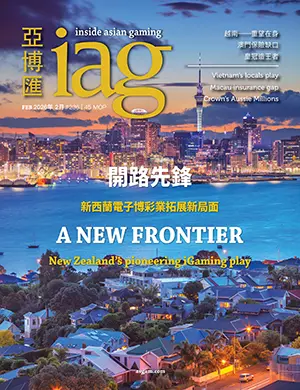日本の急成長するIR産業は、カジノ整備で不安視されるギャンブル依存症と立ち向かい続ける。この切っても切れない問題をどのようにすべきか。今回IAGは、公益社団法人「ギャンブル依存症問題を考える会」代表の田中紀子氏に話を聞いてみた。
上村 慎太郎:田中さんは3代に渡りギャンブル依存症に悩まされたと聞いています。どのような状況だったのですか?
田中 紀子:はい。祖父、父、夫、そして自分もギャンブル依存症になり、そこから回復した経緯があります。祖父はパチンコ、父は公営ギャンブル、夫は……まあ夫は何でもやってましたね。そして、自分は公営とカジノ、それから買い物依存症になりました。子供の頃、祖父のせいで貧乏で大変で、依存症がもたらす家庭不和の中で育ちました。今では自分も夫も回復しました。
上村:ギャンブル依存症かどうかは、どのように判断するのですか?
田中:これは、簡易スクリーニングテストというチェックシートを開発しました。「LOST」というものです。「L」は「Limit less」(ギャンブルの予算や時間の制限を決めない、決めても守らない)、「O」は「Once again」(勝ったお金を次のギャンブルに使おうと考える)、「S」は「Secret」(ギャンブルをした事を隠す)、そして「T」は「Take money back」(負けたらすぐに取り返したいと思う)です。これらの頭文字を合わせて「LOST」と呼んでいます。この中の2つ以上が当てはまればギャンブル依存症の可能性があります。
上村:具体的にはどのような活動をされているのでしょうか?
田中:当会は家族支援が中心です。依存症患者を抱える家族の人が当事者にどの様に対応するのかが1番重要になってくるので、そこを支援する。また本人が暴力や犯罪行為などを犯したら介入して、病院や自助グループなどに繋げる支援をします。そして、回復してきたら社会復帰のサポートをします。

上村:相談者は多いですか?
田中:多いです。深刻な人が多い。8割がパチンコ・パチスロで、あとは公営ギャンブル、最近はFXも増えています。今までほとんど依存症対策が無く、産業だけが肥大化していったという経緯があり、依存症対策を学んで来なかったのが1番の原因だと思います。
上村:今後、カジノが出来たらどうなると思いますか?
田中:国や自治体、事業者も取り組んでいますが、指定病院が増えた、保険適用になっただけで依存症対策は全然進んでおらず、ギャンブル依存症という言葉が顕在化したが支援が充実していないので、このままでは大変なことになると思います。
上村:ギャンブルは絶対的な悪なのでしょうか?
田中:いいえ、そうは考えていません。ギャンブルが楽しいものであ ったり、気分転換や娯楽である気持ちは非常にわかります。酒やゲ ームのように産業として認められているものを善悪で判断するものでは無いと思います。勘違いされやすいのですが、ギャンブルを潰そうとしているわけではなく、むしろ共存していく方向を探っていきたいと考えています。ただ、産業側の罪悪感が強くて同じテーブルに着くことを恐れていると感じています。
 上村:今後の依存症対策にどのようなシステムを期待しますか?
上村:今後の依存症対策にどのようなシステムを期待しますか?
田中:現在は業界の自主努力に任されていますので、いわゆる御用学者がほんのちょっと依存症対策をやっていることが言い訳になっているわけですよ、既存の公営にしてもパチンコにしても。自分達(運営者)のお金が流れた学者が電話相談したりとかだけ。これは利益相反の構図になっているわけです。
やるならラスベガスなどのように産業の横串を通して、運営者から税金として吸い上げて、公平性・透明性を担保する第三者機関にギャンブル依存症対策費を分配するべきだと思います。そのために官民連携して分配の枠組みをつくらないといけません。 上村:誰がどのような基準で分配先を選ぶのでしょうか?田中:1番良いのは、国が税金を吸い上げて団体に分配していく方法です。明らかな前提条件は、過去に利益相反の構図を持っていないということです。あとは、これまでの活動実績や財務の透明性とか色々あると思います。
上村:日本で有効的な対策法はどのようなものでしょうか?
田中:日本はワンストップ型ではなく、色々な団体が地域に根差し網の目のように漏らさない、アルコール依存症対策のような地域連携型が求められていると思います。あとは依存症に対する啓発です。
理解が無いために、依存症は恥と捉えられ、どんどん手遅れになるケースも多く見られます。また、回復した人が社会復帰しづらい環境も変えられればと思います。
回復過程は楽しいものなんですよ。仲間がいて、絆があ って、居場所があるから案外楽しい人生になるんです。そういう場を提供する事と依存症に対する理解が必要だと思います。