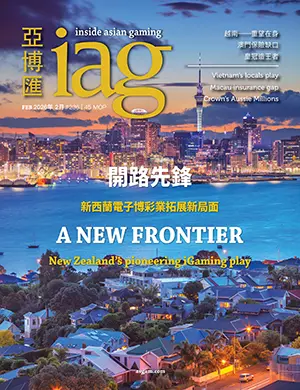1月号では日本の12の候補地を深く掘り下げた。次は、日本のIRライセンスへの関心を表明している20の事業者を二部に分けて分析していく。この号では「ビッグ4」と呼ばれるMGMリゾーツ、ギャラクシーエンターテインメントグループ、ラスベガス・サンズ、ゲンティン・シンガポールの4社を取り上げる。
Inside Asian Gaming2020年1月号の特集記事として掲載した第1部では、日本で現在行われている業界の駆け引きをお見合いパーティーになぞらえ、「女子」が候補地、そして「男子」が彼女らを口説いている候補事業者だとして話を進めた。
第1部で取り上げた12人の「女子」は、最終的にはたった3人にまで絞り込まれる予定で、現在の本命は大阪、そしてその次に最も可能性が高い横浜、長崎、和歌山が続いている。
昨年11月、国土交通省は2021年1月4日から7月30日までを、地方自治体が自ら選んだIR事業者パートナーと協力して国の政府にIR整備計画の申請を提出する期間として提案した。
 これは、それぞれの女子が2020年の残りの期間、付き合い始める男子を吟味することができるということを意味している。当然のことながら、恋のお相手は充分にいる。IAGは現在このレースの主戦場にいる20社を追っている。今回は評価や財務的に日本版IRにオールインする能力がある「ビッグ4」の会社を紹介する。残りの16社はIAG 4月のお楽しみ。
これは、それぞれの女子が2020年の残りの期間、付き合い始める男子を吟味することができるということを意味している。当然のことながら、恋のお相手は充分にいる。IAGは現在このレースの主戦場にいる20社を追っている。今回は評価や財務的に日本版IRにオールインする能力がある「ビッグ4」の会社を紹介する。残りの16社はIAG 4月のお楽しみ。
ビッグ1:巨大ゴリラ(超有力候補)
この古いジョークを聞いたことがあるだろうか。「360キロのゴリラはどこに座るのか?」 答えは「どこでも好きなところに」 この「ビ ッグ4」にいる「巨大ゴリラ」4社は、まさに世界のゲーミング業界の絶対的巨大企業だ。

MGMリゾーツ

長所:
- 大阪で最後まで生き残った男。入札の参加申請を行う唯一の事業者
- 長い間大阪にコミットしてきた
- 世界的な有名ブランドで、ラスベガスとマカオに大規模IRを持つ
短所:
- 大阪のライバルたちの撤退が憂慮すべき実態を表す可能性
- 最近行ったラスベガス資産の売却が財務上の問題を示唆している
- 長期間会長兼CEOを務めたジム・ムーレン氏が辞任する
はるか前の2014年、MGMリゾーツのビル・ホーンバックル社長が、東京で行われたみずほインベストメントコンファレンスで「MGM大阪」のプレゼンテーションを行なった。ホーンバックル氏は、もしカジノを許可する法律が充分に早い段階で通過すれば、2019年までにカジノを準備することが可能だと発言していた。大阪は2025年の5月から11月まで大阪で開催する万博に間に合うようIRをオープンすることを希望しており、その希望に対して大半の候補事業者が懸念を表明してきたことを考えると、その日程は今では滑稽に思える。MGMにとってはすでに非常に長い旅となっており、IRが初めてその扉を開くまでにはまだ少なくとも6年はかかる。
2019年1月まで「大阪ファースト」の方針を正式に発表はしていなかったものの、日本MGMリゾーツは長い間日本で2番目に大きな都市圏である大阪にその努力を集中させてきた。これによって、同社は大阪でトップを走る候補事業者の地位を獲得しており、大阪の粘り強いIR誘致の取り組みによって、大阪が誰もが認める日本のトップ候補地になってきたことを考えると、それはまた同社が日本でもトップを走っていることを意味する。

MGMの大阪でのライバルたちは、1社ずつそのプロセスから撤退し、横浜に釣られた事業者もあれば、理由を説明せずに手を引いた事業者もおり、MGMは大阪で最後まで生き残った男となった。評論家たちは、なぜ集団離脱が起こったのかを疑問に思う。大阪は多くを求め過ぎなのか?確実に、最後に生き残った男として、追う側と追われる側の力関係が変化し、今では独自の要求を行うのはMGMの側なのかもしれない。
MGMは、この「ビッグ4」にいる他の3社ほど財務基盤が健全であるとは言えず、過去12カ月間、「農場を売却」してきている。 ラスベガスにある主要施設、MGMグランド、ベラージオそしてマンダレイ・ベイの売却とリースバックによって、同社は少なくとも日本で必要になるであろう数十億米ドルのかなりの部分を手に入れた。
MGMリゾーツは2019年3月に日本のリース大手であるオリックスと提携したことで、今のところ、日本のIRライセンス獲得を目指す中でコンソーシアムを正式に結成した唯一の海外事業者となっている。
MGM日本の代表者、エド・バワーズ氏は控えめかつ真面目なスタイルで長年コツコツと取り組んできており、MGMが現在の最有力候補という地位を得たのは当然の流れだ。

ギャラクシーエンターテインメントグループ

長所:
- 健全な財務基盤。バランスシート上に現金で60億米ドルの軍資金
- アジア市場での高い適応能力を証明
- SBMとの提携がおしゃれなヨーロッパエッセンスを追加
- 複数の候補地に対してオープンな姿勢
短所:
- 現在IRを営業するのはマカオのみ
- 中国との繋がりがマイナスに受け取られる可能性
フランシス・ルイ氏率いるギャラクシーエンターテインメントグループの類まれな成功を否定できる人はいない。この会社がゲーミング事業者として活動しているのはたった14年間ほどであることをついつい忘れてしまう。最初の10年間のギャラクシーを表すのに最もぴったりな表現は、国際ゲーミング業界の誰もが認める期待の新星だったが、もう期待の新星ではない。代わりに、同社は堂々と世界のIR企業の絶対的上位グループに入っており、恐らくそこには他に1社か2社しかいない。
明らかに数は多くないものの、一部の人が、何年間にもわたって現金を絶え間なく溜め込むことを、資源の洗練されていない不十分な活用だと批判した一方で、使いたくてウズウズさせる60億米ドルもの莫大なお金を持って最後に笑っているのはギャラクシーだ。電話番号ほどの桁数の金額が日本版IRへの潜在的投資に使われることを考えると、まさにそれが目的地への切符となる。
MGMよりも少し遅れてスタートラインに立つと同時に(遅れなかった会社などあっただろうか?)、ギャラクシーは威勢よく日本での取り組みに資源を投入してきた。ギャラクシーエンターテイメントの日本オフィスでは20人以上が働いており、これは日本で最大規模のオフィスの1つだ。

ギャラクシーは、日本全国の複数の候補地で参入への取り組みを行なってきたことを隠し立てしておらず、これを「プロセスに積極的に関与している」として正当化してきた。 これによって、横浜および他の候補地に集中するという決断を下した時、同社は体裁よく大阪から撤退することができ、ルイ氏は今後も「日本への事業参入、日本政府が観光および経済での目標を達成できるよう支援することに全力を尽くす決意を持っており、GEGの健全なバランスシートおよび世界で最も成功しているIRを開発・運営しているという実績と、モンテカルロで世界初のIRデスティネーションを作り上げた150年にわたるSBMの実績が組み合わさることによって、それが実現できると信じている」と述べた。
時に冷ややかな2国間関係を考慮して、中にはギャラクシーの中国のつながりをマイナス要素として示す人がいる一方で、中国が日本へのインバウンド観光の最大の供給国であるという現実を主張する人もいるだろう。そしてこの市場に尽くすという点でのギ ャラクシーの否定できないほどの輝かしい実績は同社にとって大いに役に立つはずだ。
フランスのあらゆるものに対する日本の特別な関心を考えると(ミシュランで星を獲得しているレストランの数はパリよりも東京の方が多い)、ギャラクシーの秘密兵器が、モンテカルロで150年以上の歴史を持つ有名なモンテカルロ・カジノとオテル ド パリの所有者、ソシエテ・デ・バン・ド・メール・デ・モナコ(Société des bains de mer de Monaco:SBM)とのパートナーシップであることが後々証明されるかもしれない。モナコ公国のアルベール2世の人気が、ギャラクシー/SBMの共同入札の最後の一押しとなるか!?

ラスベガス・サンズ

長所:
- 世界で最も裕福なIR企業。IRベースのMICEにおける世界的リ ーダーとして有名
- 魅力的なシンガポール市場で世界で最も大きな利益を生み出すカジノを運営
- 政治的つながりを多く持つ
短所:
- いずれのコンソーシアムでも最大の分け前を要求する可能性が高い
- 地元での強い存在感の欠如、または日本で分かりやすく長期的に活動していないことが、権利意識と捉えられる可能性がある
- 他社と上手くやっていけなかった歴史がある
1999年5月3日月曜日、ラスベガス・ストリップに新しいカジノがオープンした。幾分、想像力にかけているのか、または敬意を表してということなのか、1952年からその場所にあった以前のホテルカジノから単純にその名前がつけられた。
そのカジノの名がサンズ。そして2008年の世界金融危機中に起こった1度の酷いつまずきを別にすると、21年間にわたってそのカジノは利益を生み出し続けてきた。そしてオーナーであるシェルドン・アデルソン氏は、フォーブスの2019年度米国長者番付『フォーブス400』で、17番目に裕福なアメリカ人にランクインするまでになった。またそれによってラスベガス・サンズは世界最大のIR企業へと成長し、時価総額は500億米ドルにのぼっている。
はったりやこけおどしと言われることもあれば、先見の明があり天才だと言われることもあるその人物像で有名なアデルソン氏は、世界のゲーミング業界で最も有名な区域、コタイを作り上げた男だ。ぎりぎり2平方キロメートルあるかどうかの広さの区域、これがマカオのIR業界、つまりは世界のIR業界のとっての開始点であり、過去10年間毎年米ドルで何百億というゲーミング粗収益(GGR)を生み出してきた。サンズはコタイストリップ沿いに3つの施設を管理している。ザ・ベネチアン・マカオ、ザ・パリジャン・マカオそしてサンズコタイセントラル(まもなくザ・ロンドナーに生まれ変わる)。
さらにその上、サンズは2010年に誕生したシンガポールIR業界のライセンスを勝ち取った2社のうちの1社であり、その結果があの有名なマリーナベイ・サンズだ。しばしば日本が独自のIR業界を生み出す中で、達成しようとしているもの全ての指針として関係者によって高く評価されている。

サンズとギャラクシーは、元々20年ほど前には、マカオのライセンス獲得を目指す中でのパートナーであったにもかかわらず、または一部そのせいで、現在はマカオで最大の競争相手となっている。2社が関係を解消して以来、アデルソン氏とルイ氏という2人のリーダーは、世界最大のゲーミング市場でマーケットシェアをめぐって激しい戦いを繰り広げてきた。
何年間も、サンズはその競争の中で鼻先のリードを保ってきたが、サンズ帝国には弱点がある。そのカリスマ性のある起業家精神にあふれたリーダーが、非ホジキンリンパ腫の治療を受けているのだ。ただし、アデルソン氏が数カ月職場を離れた後に復帰したことは留意しておかなければならない。アデルソン氏の健康を引き合いに出すのはフェアでないかもしれないが、それがこの状況の現実だ。
2019年、フランシス・ルイ氏は、アジアゲーミング業界で最も影響力のある50人を選ぶIAGパワー50ランキング(iagpower50.comを参照)で1位の座に輝き、たった2ポイントの差でアデルソン氏をかわした(7,764ポイント対7,762ポイント)。それまでの7年間、順位は逆でアデルソン氏がトップの座を維持していた。その際、審査員はこのようなコメントを残した。「現時点ではサンズの方が大きな会社だが、影響力ではルイ氏の方が大きい」
「より大きな会社」が日本でゴールテープを切ることができるかどうかは、まだ分からない。多くの人がアデルソン氏のドナルド・トランプ米大統領への資金援助、そしてトランプ大統領と(日本版IRの熱烈な支持者である)安倍首相との関係を、サンズが成功する可能性が高い理由として挙げている。しかし、中にはサンズは柔軟性がない事で有名だという事実を指摘する人もおり、サンズは「自分たちのやり方」で物事を進めることにこだわり、パートナーシップに難色を示す傾向にあるという。これは日本のIR業界で徐々にはっきりしてきたように思えるコンソーシアムベースのアプローチには上手くはまらない可能性がある。
誰が正しいかは時間が経たなければ分からない。

ゲンティン・シンガポール

長所:
- 日本では「レーダーに映りこまないよう」飛行することを選ん でいる
- 日本にとって魅力的なシンガポール市場
- 効果的な責任あるゲーミング対策におけるシンガポールの 強力な実績
短所:
- 日本では「レーダーに映りこまないよう」飛行することを選んでいる
- 英国、米国、バハマ市場では、いい結果ばかりというわけではない
- 横浜の開発上限額を100億米ドルに設定した
この段階で、4社中最も知名度の低いゲンティンではあるが、55年の歴史を持つ世界のゲーム業界における巨人だ。当時ゲンティン・ハイランドとして知られていた施設(現在のリゾートワールド・ゲンティン)は、マレーシア人のタン・スリ・リム・ゴートン氏によって設立され、長年に渡る厳しい山岳工事の後、1971年に開業した。マレーシアの首都クアラルンプールから車で北へ約1時間の場所にあるリゾートワールド・ゲンティンは、現在でもグループ全体にとって心のふるさとであり、親会社のゲンティン・バーハッドが所有している。
その後の数十年間で、大きな成長を遂げ、2003年にリム・ゴートン氏から息子のタン・スリ・リム・コック・タイ氏に引き継がれた。2019年のIAGパワー 50リストで4位にランク付けされたリム・コ ック・タイ氏は、現在も会社の会長を務めており、マレーシア、シンガポール、イギリス、バハマ、フィリピン、ニューヨーク州、およびラスベガス(建設中)にあるリゾートワールドブランドの資産でもって世界帝国を監視し続けている。 ただし「マカオにはない」ということには注目しておかねばならない。
ゲンティンは、抜け目なく、今世紀最初の10年間に行われたシンガポールのライセンス手続きで最終的に勝ち残った2社のうちの1社である上場子会社、ゲンティン・シンガポールを通じて日本でのキャンペーンを主導することを決めた(前述したように、もう一方の勝者はサンズで、マリーナベイ・サンズの成功につながった)。日本は少なくともある程度は、シンガポールモデルにずっと憧れてきた。地元住民への高額の入場料、ゲーミングフロアの面積への厳しい制限、そしてジャンケットへの抵抗感など日本がこれまでに計画した規則の中にはシンガポールの特徴がいくつか見られる。シンガポールの非常に清潔なイメージもまた、日本の富裕層の感性にうまくはまっている。

ゲンティン・シンガポールの最も特筆すべき点は、断固たる「ノ ーコメント」ポリシーであり、これは長年、ゲンティンの広報活動の特徴となっている。これには賛否両論がある。賛成派を後押しするのが、「話して疑いを晴らすよりも、沈黙して愚か者と思われる方がよい」という格言だ。 一方、反対派意見の代表として挙がるのは、「 自然は真空を嫌う」だ。
今日のようなソーシャルメディアや誰でも利用できるインスタントコミュニケーションプラットフォームの時代では、さまざまなコメンテーターや一般の人々でさえも、企業が独自に発信しないなら、自分たちが喜んで話を作り上げるだろう。
ゲンティン・シンガポールの社長兼CEOのタン・ヒー・テック氏は、珍しく公の場、そのほとんどが日本のIR業界周辺で現れ始めている新しい業界見本市、に姿を表した際、当たり障りがないとはいえ会社を売り込むのに役立つ仕事をしてきた。この当たり障りのなさは計画的である可能性が高く、舞台裏でどのような工作が行われているのかは誰にもわからない。
ゲンティンはシンガポールで目標を達成することができたが、それは基本的にはホームでの試合だった。ゲンティンがアウェイでどのように闘うかは今後を見守ることにしよう。