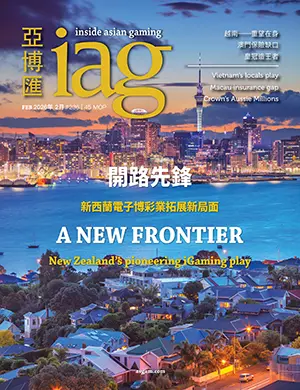マカオが責任あるゲーミングの推進においてどの程度まで歩みを進めたのか、マカオコマーシャルゲーミング研究所所長のデイビス・フォン教授が説明する。
マカオでの「責任あるゲーミング推進活動」の第一人者、デイビス・フォン教授は、マカオ特別行政区政府のために40以上のギャンブルおよび観光関連の研究プロジェクトを実施してきた。
教授は、コマーシャルゲーミング研究所所長という役職の他に、2017年からは現地の経済開発委員会顧問、2014年からは人材開発委員会委員、そして2015年からは統計諮問委員会の一員(マカオ大学代表)も務めてきた。
また第6期マカオ立法会議員も務めている。Inside Asian Gam-ingはフォン教授にインタビューを行い、教授が率いる責任あるゲ ーミング推進活動でマカオがどの程度達成したのか、そしてギャンブル依存症を持つ人を特定し支援するための最新の取り組みについて話を伺った。
オスカー・ギハーロ:つい最近、責任あるギャンブリング(RG)プロモーション2019を立ち上げられましたね。今年のRGの取り組みについて教えていただけますか?
デイビス・フォン:今回初めて我々は、同じプラットフォームにいる全ての利害関係者を招き、来年どのような取り組みを行うかを提示してもらいました。これまでは、主催者として単に我々が何をするかを発表していただけでした。ですのでカジノ事業者6社と3つのNGOの代表者を含む全ての関係者が翌年にどのような取り組みを行う予定かを紹介してもらうのは今回が初めてになります。
これは私にとって様々な利害関係者の計画全体を見る初めての機会でしたので、比較を行うことができました。以前は全ての関係者が単に社内トレーニング、社内プロモーションに焦点を当てていたのに対して、今回は多くの取り組みで顧客、従業員、家族、そしてコミュニティに焦点を当てているのが見て取れました。RGの取り組みというものはかなりクリエイティブかつ、多様化しています。
以前は責任あるゲーミングというものがどうあるべきかというメッセージを伝えるための非常に受け身のプロモーションでした。今年は参加型のゲームやイベントなども見られます。取り組みの創造性も楽しみも増しています。

OG:観光客をターゲットにした主な取り組みにはどのようなものがありますか?
DF:観光客というのは常に主要なターゲットであり、主催者(マカオ政府)は実際多くの資源を投入しました。ボーダーゲートには、過去3年間毎年3カ月ずつ観光客をターゲットにした巨大な看板を設置しています。また、政府の財源を使ってデジタルディスプレイに広告も流しています。この他にも、DICJはいくつかの現地NGOのスポンサーとなり、中国でRGセミナーを開催してもらっています。すでに中国大陸で5つのセミナーを後援し、あともう一つ予定されていますので、過去3年間で6つになります。
OG:マカオにおけるギャンブル依存症の最近の傾向をどう説明されますか?
DF:大幅に改善しました。期待通りであり、満足していると言えます。サンズが最初のIR、サンズ・マカオをオープンする前、第一回有病率調査は2003年に実施されました。その当時1.8%が病的ギャンブラー、さらに2.6%がギャンブル依存症に分類されましたので、合わせて約4.4%がギャンブル障害に苦しんでいました。
最新の数字は2016年のもので合計約2.5%でした。2019年についてはまだ最終的なレポートをまとめているところです。ですので、満足していると言いたいと思います。しかし繰り返しますが、さらに多くのカジノやIRが開業し、そのアクセスが容易になっていますので、継続した努力、そしてこの流れを保ち続けていかなければなりません。
OG:典型的なギャンブル依存症患者というようなものはあるのでしょうか?
DF:複数のグループ間で統計上の違いが見られます。カジノやサッカーくじのギャンブラーは、マージャンなどの他の形式のギャンブルやマカオジョッキークラブなどのソーシャルギャンブルと比べてギャンブル中毒になる可能性が高いと言えます。過去16年間の統計を見ると、マージャンやジョッキークラブのギャンブラーが中毒にまでなることは非常に稀な一方で、カジノ、サッカーくじではギャンブル依存がはるかに進みやすくなっています。これはマカオでは、ギャンブル依存症患者は基本的にカジノでの賭けまたはサッカーくじを行なっていることを意味します。その2つを合わせると約90%に達します。
OG:ギャンブル依存症との戦いの中でマカオ固有の課題にはどのようなものがありますか?
DF:マカオには大きな課題が1つあります。それが学校です。率直に言って、学校は責任あるゲーミングの取り組みに関してかなり保守的です。彼らは責任あるゲーミングを直接的に推進したがりません。というのも学校の視点から見ると、ギャンブルというもの自体が存在しないからです。それが、我々にとって子供たちが学校を出る前に責任あるゲーミングを推進するのが非常に難しい理由です。そのために隔たりが残ります。
その後彼らが21歳になった時、彼らは好奇心旺盛であり、周りには多くのカジノがあります。中に足を踏み入れ、コントロールを失ってしまう可能性があるのです。我々はこれらの障壁を克服する努力をしています。いくつかの教材を開発し、学校がお金の価値、資産の価値そして最後にギャンブルの価値について生徒に教える授業を年に1回行えるようにしました。直接的に責任あるゲーミングを推進する代わりに、価値の理解に焦点を当てたことで、校長たちはこのアイデアを受け入れました。
OG:現地のゲーミング市場が徐々にVIP中心の環境からマス市場へと進化しているのが見られています。このプロセスはギャンブル依存症の数字に反映されてきていますか?ギャンブル依存症に関してVIPとマスのプレイヤーの間に違いはありますか?
DF:実際、有病率の分野でいわゆるVIPとVIP以外のギャンブラーの間で統計的有意性は見つかっていません。しかしながら、VIPに関しては、データを集めるのが大変難しいということがあります。というのもVIPはあまり目立たず、対面でインタビューを行うのが非常に難しいからです。ですので、我々がVIPとVIP以外の層を比較できるような妥当な調査結果を出せるかどうかに関してはあまり確かではありません。かなり興味深い質問であり、未解決の問題です。
しかしながらVIPについては、もし例えば1年に1、2回ギャンブルする場合、もし大きな賭けを行ったとしても、それがギャンブル依存症であるということにはなりません。私の理解でいうと、ギャンブル障害というのは、過去12カ月間で継続的に発生していることを意味しており、いくつかの症状、少なくとも9つの特定症状のうちの4つの症状を示している必要があります。
もしそれに当てはまっている場合はギャンブル障害を持つと分類されるかもしれませんが、年に1,2回ギャンブルする場合、たとえ1,000万香港ドル(約1億3,900万円)を失おうとも、ギャンブル依存症患者またはギャンブル障害を患っているということにはなりません。単に大きな賭けをしているだけです。
OG:ギャンブル依存症を解決する万国共通の方法というのはあるのでしょうか?それともそれぞれの地域で独自のアプローチを開発する必要があるのでしょうか?
DF:責任あるゲーミングの推進に関わって11年、文化の違いというものが最大の障壁の1つだということが分かりました。独自のテーマやスローガンを展開する際、ギャンブラーの心に訴えかける必要があります。そうするためには、おそらく研究者のような現地文化を深く理解している人物が必要です。