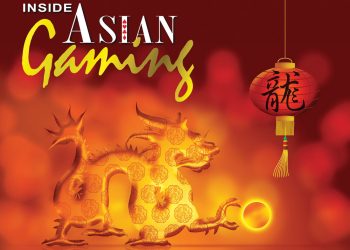Inside Asian Gamingが、グレーター・トロントYMCAで若者のギャンブル認知プログラムを行うアデラ・コルホン氏とミーナ・ハザー氏と、ギャンブル依存症へのスティグマの影響についてマカオでの最近のセミナーで話し合った。
ギャンブル依存症は、ゲーミング業界の全領域を通じた共通の問題だ。政府と事業者は法律、機関、政策およびアクションを設置することで社会への影響を最小限にしようと先頭に立って動いている。しかしこれらの対策の効果は、最近認識されるようになってきた数式の1つの要素によって条件づけられる。それがスティグマという概念だ。
スティグマの由来は、古代ギリシャで特定の人々(大抵は犯罪者だが奴隷も)の体の見える場所に焼いた鉄製の印を押し当てて、他人からその立場が一目瞭然となることを目的とした烙印だ。
現代において、この表現は中毒やメンタルヘルス問題、ギャンブル依存症、または社会に影響を与えるその他の重大な問題に苦しむ人 々を我々がどう見るかということを表している。
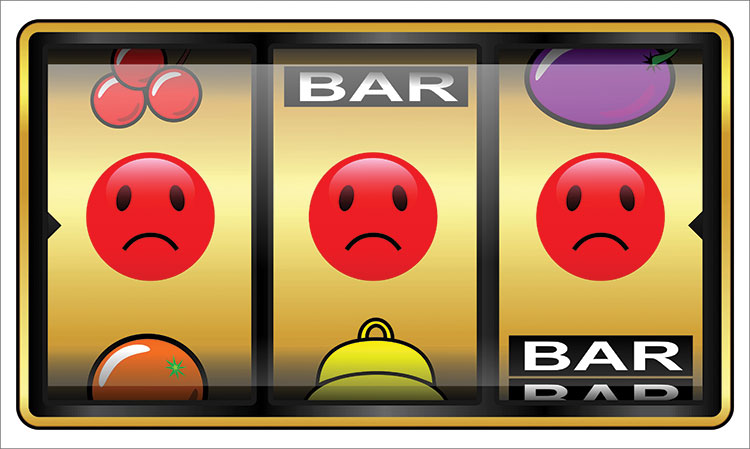 グレーター・トロントYMCAで若者のギャンブル認知プログラム(Youth Gambling Awareness Program)のバイリンガル地方ディレクターを務めるミーナ・ハザー氏は、「目には見えない印ですが、それでも自分たちの判断に利用しているものなのです」と語る。
グレーター・トロントYMCAで若者のギャンブル認知プログラム(Youth Gambling Awareness Program)のバイリンガル地方ディレクターを務めるミーナ・ハザー氏は、「目には見えない印ですが、それでも自分たちの判断に利用しているものなのです」と語る。
ハザー氏によると、そのようなスティグマは「差別につながり、これらの人々は雇用、住居といった基本的人権を否定されています。そしてもう一つの問題は、彼らはすでに孤立しており、すでに一人で苦しんでいるということです。
この疎外感は強固な障壁となり、彼らが自身の問題に向き合う妨げとなる。ハザー氏はそれを「ギャンブル依存症の問題に関して助けを求める際の最も大きな壁」であると説明する。
大トロントYMCAは、ギャンブル依存症と、多くの場合にそれに伴うスティグマへの認識を高めることで、カナダと世界の両方でそのような疎外感を無くしていくを目指している。
ハザー氏は、「我々はスティグマを減らすために何ができるかということに焦点を当てています」と語り、そのプロセスには「その状況を表現する際に使用する言葉を変化させ、人々の態度を変化させることが含まれており、それが人々の行動の変化につながる」と説明する。
ギャンブル依存症とスティグマへのアプローチとは、その人たちが精神的な病に苦しんでいること、そして彼らの行動は症状であると考えることだ。
ハザー氏は、「それは薬物やアルコールと全く同じ方法で脳に影響を与えます。行動を変化させるために、我々は親身になる必要があり、質問しなければなりません。その人物についてより詳しく知り、その人が問題を抱えているかどうかを知る必要があります。より深い根本原因があるかもしれません」
教育がカギ
スティグマがギャンブル依存症を患う人々が背負う重荷である一方で、スティグマイゼーション(烙印を押す行為)はこのプロセスのきっかけとなる態度である。
ハザー氏は「私たちは烙印を押されていると感じる全く同じ理由で人に烙印を押します。だから自分自身の判断を意識しなければなりません」と話す。
グレータートロントYMCAの国及び地方プログラム担当ゼネラルマネージャー、アデラ・コルホン氏は、スティグマとスティグマイゼーションの問題に対処する際の知識の重要な役割を強調する。
 コルホン氏は、「健康上の問題であり、ギャンブルを問題として見るべきではありません。より重要なのは認識を作り出すということで、『ギャンブルがどういうもので、何に足を踏み入れようとしているかを理解している』、そしてギャンブル依存症の状態にいると分かった人たちがどこに、どのようにして助けを求めるかといったことを分か っているといった状況です」と話す。
コルホン氏は、「健康上の問題であり、ギャンブルを問題として見るべきではありません。より重要なのは認識を作り出すということで、『ギャンブルがどういうもので、何に足を踏み入れようとしているかを理解している』、そしてギャンブル依存症の状態にいると分かった人たちがどこに、どのようにして助けを求めるかといったことを分か っているといった状況です」と話す。
認識を作り出すということ以上に、ハザー氏はギャンブル依存症はより広い意味での疎外感に端を発していると指摘する。精神疾患とうつの主な原因はつながりと目的意識の欠如であるというアメリカの作家、ヨハン・ハリの理論に言及し、ハザー氏は「あらゆる種類の中毒活動または行動に関して、治療というのはそれを断つことではありません。
つながりや目的意識を見つけることは、彼らがどのようにやって来てどのようにギャンブルにアプローチするかという点で、人によって形や形式が異なる可能性があります」と語る。